「外航船の航海士って、どんな仕事をしているんだろう?」
漠然としたイメージはあるけれど、具体的な仕事内容や1日の流れなど詳しいことは知らない方も多いのではないでしょうか?
子供の頃に船旅に憧れた、地図を見るのが好きだった、そんな皆さんにとって、航海士は夢を叶える職業と言えるかもしれません。
しかし、航海士の仕事は決して楽ではありません。厳しい自然環境の中、長期間にわたる航海で、船舶と乗組員の安全を守るという大きな責任を担います。
今回は、そんな外航船航海士のリアルな働き方について、現役航海士の筆者が自身の経験をもとに実際の1日のスケジュールを詳しくご紹介します。
将来は、グローバルに活躍できる仕事に就きたい。
安定した収入と、やりがいのある仕事を求めている。
そのように考えている学生の皆さんには、ぜひ知ってほしい職業です。
このページでは、航海士の仕事内容、1日のスケジュール、給与、居住環境など、キャリアを考える上で必要な情報を筆者の経験をもとに解説していきますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
「ただ船を操縦するだけじゃない」外航船航海士のリアルな仕事と役割
外航船航海士と聞いてどのようなことをイメージするでしょうか。
外航船とは、日本の港と外国の港を結ぶ、国際海上輸送を担う船のことです。 コンテナ船やタンカー、自動車専用船など、様々な種類の船が世界中を駆け巡り、人々の生活を世界の物流を支えています。

国土交通省の2022年のデータによると、海上輸送は、日本の国際貨物輸送量全体に占める割合が約99.7%と、依然として圧倒的なシェアを誇っていることが分かります。
今回は現役外航船航海士である筆者が数年勤務した経験をもとに、仕事の内容や魅力と現実を解説していきます。
航海士とは?
そもそも航海士とは船の上ではどのようなことをするのでしょうか?なんとなくイメージはできるものの、具体的な業務内容まで知っている人はそう多くはないでしょう。
船を動かすには、多くの人が力を合わせなければなりません。現場では船長を筆頭に、航海士、機関士、甲板員、機関員、フェリーや客船などでは事務員など、それぞれ専門的な知識や技術をもち船の安全運航を支えています。
その中でも、航海士は船の運航を担当しています。 具体的には、航海当直をはじめとして航路の計画・決定、船の操縦、貨物の管理、船舶の保守管理などがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

航海当直
航海士の労働時間の大半を占める仕事に航海当直があります。基本的には3人で24時間をカバーし、4時間ごとに交代します。それぞれパーゼロ(8時-12時,20時-24時),ゼロヨン(0時-4時,12時-16時),ヨンパー(4時-8時.16時-20時)と呼びます。会社や船・乗組員の数にもよりまずが三等航海士は主にパーゼロを担当します。航海士は基本的に一日あたり8時間の航海当直を担います。

航路の計画・決定
気象や海象、潮流などを考慮し、安全かつ効率的な航路を決定します。
商船の航海では、船・貨物を安全に運ぶことは大前提として、期日を守ることも非常に重要です。
あらかじめ航路を決めていても、突然、荷物の揚地が変更になったり、台風の発生により航路の修正が求められることもしばしばあります。
船の操縦
レーダーやGPSなどの航海計器を用いて、船を安全に操縦します。
天候に合わせて、船が揺れにくくしたり、ほかの船と安全に行き交うことができるように操縦する必要があります。また、船体の塗装を行っているときは雨域を避けたりもします。

貨物の管理
貨物の積み付けや荷降ろしを監督し、安全に輸送されるよう管理します。貨物は積んで運ぶだけではありません。液化ガスなどは圧力や温度管理をしなければなりませんし、貨物を無事に港へ届けなければなりません。基本的にどの船種も貨物の管理は航海士が担っています。
船舶の保守管理
船体の点検や整備を行い、常に安全な状態を保ちます。船は常に潮風を浴びているので、何もせずに放置していると錆びて破損や事故のリスクがあがる上に、船の寿命を縮めてしまいます。適切なメンテナンスを行えるかどうかも航海士に必要な能力です。
通信業務
かつては通信士も乗っていましたが、通信機器が発展したことにより現在では航海士が兼任しています。遭難した際に使用する機器の保守やWi-Fiなどの管理も通信業務に含まれます。
ほかの職務については以下のページでそれぞれ解説しているのでもっと知りたいなという方は参照してください。
航海士になるためにはどんな資格が必要か
航海士の資格としては海技士(航海)の6級から1級までありますが、国際航海に従事する船舶に航海士として乗船するためには最低でも三級海技士の資格が必要です。詳しい免許の取得方法については以下の記事で解説しているので気になる方はご参照ください。
「4ヶ月働き、2ヶ月遊ぶ」陸上職にはない究極のライフサイクル

船の仕事は高収入である一方で、激務でしんどい・ブラックといった噂も商船系の学校に通う学生ならば聞いたことがあるかもしれません。確かに忙しくてあまり寝られない日もあります。しかしながら、航路や船種にもよりますが、乗船中ずっと眠れない日が続くのかと言われるとまったくそのようなことはありません。
外航船に乗り組む航海士・機関士は多くの会社では6か月乗船して3か月休むというのが主流です。会社によっては9か月継続して乗船することもあります。
しかし、最近では働き方改革のあおりを受けて海上でも乗船期間を短縮する動きが活発になり、4か月乗船2か月休みの会社も増えてきております。
どちらが良いのか様々な意見があり、それぞれ以下のようなメリットデメリットがあります。
技能を身につける機会が多い
一度仕事に慣れると労働負荷が少なくて済む
まとまって大きなお金を貯められる
休暇が長くなる
仕事に慣れてきた頃に下船
1回の乗船経験が浅くなってしまう
人の交代が激しく人間関係が変わりやすい
家族と離れ離れになる期間が短い
休暇は長ければ長いほうがいいに決まってると思っていましたが、あまりにも長すぎると貯金も尽きてきますし、毎日にメリハリもなく退屈になってきます。3か月以上休んでいるとさすがにそろそろ働いてもいいかなと思えてきます。
乗船中のスケジュール
実際に経験したスケジュール
まず大前提として、船種ごとに荷役時間や出入港にかかる時間は異なるので一概にこれだけ働かなければならないというわけではありません。そのため今回は過去に筆者が経験した2日間の出入港のスケジュールを紹介します。
1、出入港
- 00:30当直後の見回り・巡検終了
当直後は火災や異常が起きていないか船内を巡検します。
- 06:00起床・身支度
- 06:30航海当直・船長補佐
港が近づくと操船の難易度も上がるので、基本的には船長がメインで操船しその補佐を三等航海士が行います。
- 11:00着岸・荷役の準備
港へ到着したら、休む間もなく荷役の準備が始まります。
- 14:00荷役会議補佐・荷役開始・昼食
隙を見て昼食をとり、荷役が始まれば荷役の補佐・当直をします。
- 20:00荷役当直終了・休息
- 03:002日目/荷役当直開始
- 10:00荷役終了・撤収作業開始
荷役が無事に終わり、片付けを始めます。
- 12:00撤収作業終了
荷役がひと段落し、休息し昼食を摂ります。
- 14:00出港準備
出港できるように航海計器のテスト・起動を行います。
- 15:00出港・船長補佐
出港後も船が多く危険なので船長の補佐を行います。
- 17:00船長補佐終了
出港しひと段落すれば、休息し夜の当直に備えます。
- 20:00航海当直
- 24:00航海当直終了
夜の当直が終わればまた、航海の日々が始まります。
2、通常航海(大洋航海中)
基本的に朝晩の当直と当直後の夜間巡検は必ず毎日行わなければなりません。しかし、午後の勤務時間に関しては、機械のトラブルであったり、日々の火災訓練(操練)などで多少の増減はあります。上司から任せられている仕事が立て込んでいれば13時から17時まで働きますし、特に仕事がなければ当直以外の時間は娯楽や休息・勉強に充てることもあります。ほとんどの日は午後も働くか勉強するかのどちらかですので一日8時間労働と勘違いをして船乗りになってしまうと痛い目を見ると思います。
- 00:30当直後の見回り・巡検
- 01:00就寝準備・娯楽
寝る前の時間はスマホをいじったり、翌日の準備をしたり自由に過ごせます。
- 01:30就寝
- 07:00起床・朝食
朝食は船によっては個別に用意されていたり、ビュッフェスタイルだったりします。
- 07:50航海当直・引き継ぎ開始
引継ぎのために10分から5分前には船橋に上がります。
- 12:15航海当直終了・記録など
航海当直を引き継いだ後は、航海日誌(ログブック)を記録します。4時間での航海距離や変針、気象などを書きます。
- 13:00午後の業務開始
日によっては操練(火災訓練や総員退船の訓練)や担当機器のメンテナンス、甲板部の作業の補佐を行ったりします。
- 16:00午後の業務終了
疲れがたまっている日や、仕事の締め切りに余裕があれば早く休むこともあります。空いた時間で勉強することもあります。
- 18:00夕食
夕食後は自由時間なので、部屋で読書したり、集まってテレビゲームをすることもあります。船の雰囲気によってこの時間の過ごし方は変わってきます。近年ではアルコールがらみのトラブルが頻発し規制が厳しくなったこともあり、飲み会の頻度も一昔前よりかなり減りました。
- 19:45航海当直・引き継ぎ開始
- 24:00当直終了・巡検へ
3、船内休日
船内休日に関しては各船会社や船長によって考え方がさまざまであり、完全にまる1日休ませてくれる船もあれば半年間まったく休みがない船もあります。こればっかりは入社前にエントリーしている会社に確認したほうがいいかもしれません。
- 00:30当直後の見回り・巡検
- 01:00就寝準備・娯楽
- 01:30就寝
- 09:00起床
乗船中は一度に長く寝るチャンスが少ないので、休日は長めに寝ることが多いです。休日でも他の人にまかせることが 難しい業務は自分でしなければなりません。仕事が溜まっていたりすると休日に済ませることもしばしば。
- 12:00昼食
土日などは会社からのメールもほとんど来ないので船も当直以外の業務は極力しません。午後は自由に過ごします。
- 18:00夕食
- 19:45航海当直・引き継ぎ開始
- 24:00当直終了・巡検へ
以上が筆者の経験をもとにした三等航海士の勤務時間の例です。出入港が重なると、当然睡眠時間も細切れになったり、ほとんど寝れない時間が続いたりすることもありますが、航海が始まってしまえば、長めに休息を取ることもできます。
月の労働時間は出入港が少ない月では260時間程度で多い月では320時間を超えることもありました。
令和5年の国土交通省のデータによれば、外航船舶に乗り組む日本人船員の月間総労働時間は219.4時間でした。これは、職位関係なくすべての外航船員の平均であることから少なめになっているのかもしれません。三等航海士は当直に加えて、こまごました雑務を任せられることが多いので船内でも労働時間が長くなる傾向があります。
じゃあ、実際どれくらい給料もらえるの?
実際これだけ働いてどのくらい給料がもらえるのかズバリ気になると思います。
令和5年の船員労働統計によると外航船員の1か月あたりの平均給与は653,235円(年齢37.2歳、経験年数11. 8年)だそうです。会社の規模によって多少の上下はあるとは思いますが、他社の知人に聞いてみてもこの数字は間違いではなさそうです。実際、筆者も入社して4年目でも1000万円前後はもらえていました。しかし、年間の乗船日数によって手当てが変動するので、給料のブレは大きいです。
賞与も加味すると30代には額面1,000万円も夢ではないでしょう。乗船中限界まで働いて年間3か月前後のまとまった休暇をもらえて、稼げるこんなに魅力的な職業はないと思います。
つい数年前までは、人手不足によって年間10か月乗船せざるを得なく、休暇が全然もらえないということもありました。しかし、最近では陸での働き方改革や若手の離職を防ぐために業界全体で雇用条件の改善の動きが活発になっていると感じます。
【ザイテク】海の上は「強制貯蓄」天国?資産が勝手に増える仕組み
外航船員の給料が高いのはもちろんですが、それ以上に「お金を使う場所がない」というのが資産形成における最強の武器です。
- 食費・光熱費・家賃がタダ: 乗船中はこれらが全て会社負担です。
- 誘惑がない: 海の上にはコンビニも居酒屋もありません。
つまり、陸上のサラリーマンなら生活費で消えていくお金が、船乗りなら「給料のほぼ全額がそのまま口座に残る」という状態になります。
私はこの環境を活かして、毎月10万円を自動で投資信託(S&P500など)に積み立てる設定にしています。 「物理的にお金を使えない期間」を「強制的な資産形成期間」に変えることで、20代でも驚くスピードで資産を築くことができます。
乗船する船種
ここで注意していただきたいのは、乗船する船種によって給料も労働環境も左右されてくるということです。基本的には日本人船員というのは、会社と雇用契約を結んで会社の指示で乗船していきます。なので就職してからこの船種しか乗りたくないというようなわがままは通用しません。また、会社ごとに運行管理・配乗をしている船種も様々であることから、乗りたい船種がある人は就職前にしっかり調査したほうがいいでしょう。
ここでは簡単に主に外航船で多くある船種の特徴を紹介します。筆者の主観も多分に含まれるのでご注意ください。
タンカー(ガス船・原油・プロダクト)
出入港は少ないが、たまに複数港で荷役しなければならいなことがあります。SIRE(Ship Inspection Report : オイルメジャーによる船の検査)の対策が必要で、安全管理体制が厳しいです。また入港する国がマイナーだったり、治安が悪い地域に行くこともしばしばあります。。
コンテナ船・自動車専用運搬船
出入港が多い/連続で数日間出入港となることもありますが、荷役の負担は比較的少ないです。入港頻度も高いためPSC(Port State Control)の対応が大変です。入港する国は上陸が魅力的な国であることが多いため上陸が充実します。
バルカー(バルクキャリアー)
出入港の回数は少ないため、荷役の負担も少ないです。しかし、複数港で揚荷することもあります。
3食・個室・掃除付き?「船上ホテル暮らし」の居住環境を公開
ここでは簡単に外航船での居住環境について解説します。
船齢や船種によって、部屋の広さや綺麗さは様々ですが一般的な共通部分を筆者の経験をもとに説明します。
ネットは繋がる?Starlink導入で激変した「通信事情」
以前まではインマルサットという中軌道衛星システムで、通信速度も通信コストもいまいちでした。LINEを送るにも数分かかり、YouTubeなどもってのほかです。しかし、最近では低軌道衛星システムのスターリンクの導入が進んでおり、目まぐるしく改善されています。基本的なスマホの使用はもちろんのこと、テレビ電話もスムーズにできます。
ちなみに、ここ数年で船のネット環境は劇的に進化しました。 以前はメールがやっとでしたが、最新の「Starlink」導入船ではYouTubeも見れるようになっています。
ただし、「使い放題ではない(制限がある)」などの落とし穴もあるので、詳しくはこちらの記事で解説しています。
水回り
水回りはトイレ・シャワー・水面台が一体になっているのが一般的で各個室に設置されています。好きなタイミングで使用できますし、航海中は造水機で清水を作っているので使用回数も制限はありません。

娯楽設備
船上での娯楽には漫画や雑誌、テレビゲームなどありますが、最近では電子書籍を持参して読むことも多いです。運動はデッキ上を散歩・ランニングしたり、ジムで筋トレをしたりなどがあります。一通りの筋トレ器具がある船が外航船には多いです。写真は実際に筆者が過去に乗船した船のジムです。

外航船航海士のやりがいと魅力(達成感、自己成長、国際性など)
今回は筆者が経験した外航船航海士の生活について解説しました。
外航船員には長期休暇が魅力的なのはもちろんのこと、多忙な日々を乗り越えて下船を迎えたときの達成感を超えるものはありません。毎度の乗船で知識や経験も増えていき仕事をこなすのもうまくなっていくので慣れるまでは大変ですが、楽しいこともたくさんあります。日常の中では見れない景色であったり、いろいろな国の人との出会いなど船に乗っていると様々な経験ができます。
一方で、長時間労働や閉鎖的な環境のストレスがあるのは事実です。また、長い期間、家族と離れ離れになるため退職してしまう人も少なくはありません。人を選ぶ職業ですので自身の特性と職業がマッチしているか十分に検討することをお勧めします。

最後に
以上が現役外航船航海士が実際に経験した船の生活や仕事の実情についてお伝えしました。筆者もまだまだ若輩者ですが、これから船乗りを目指す方の手助けになれたら幸いです。
外航船員は確かに高給取りですが、船の生活環境が悪ければ、せっかくのお金を使う楽しみもありません。
私が実際に給料を使って揃えた、「船上生活のストレスを激減させる神アイテム」をまとめました。 これから乗船する方は、初任給が入る前にぜひチェックしてみてください(自己投資として元は取れます)。
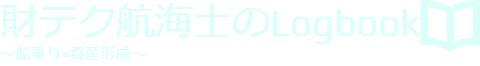







コメント