海上での船舶の追い越しには厳格なルールがあります。
特に、航行する場所によって適用される法律が異なり、それぞれのルールを守らなければなりません。
今回は、「海上衝突予防法」「海上交通安全法」「港則法」における追い越しルールの違いや相互の関係性についてわかりやすく解説します!
海技士試験でもよく問われるのでしっかり理解しましょう。
1. 海上での追い越しはどんなルールがあるの?
海上での追い越しは、道路とは違い「船の操縦性能(動きやすさ)」「波や風の影響」「輻輳度(混雑度)」などを考慮した法律が定められています。
主に適用される法律は以下の3つです。
✅ 海上衝突予防法(一般海域で適用)
✅ 海上交通安全法(東京湾・伊勢湾・瀬戸内海などの特定海域で適用)
✅ 港則法(港湾内の船舶交通を規制)
それぞれの法律の適用範囲と追い越しに関するルールを詳しく見ていきましょう!
1.1 海上衝突予防法
どんな場所で適用される?
👉 すべての海域に適用される、船舶の衝突を防ぐための基本ルール。
追い越しはできる?
👉 追い越し可能!
ただし、追い越す船(避航船)が避航義務を負い、追い越される船(保持船)は針路・速力を保持する義務があります。
追越し船の航法
第十三条 追越し船は、この法律の他の規定にかかわらず、追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けなければならない。
海上衝突予防法第13条
2 船舶の正横後二十二度三十分を超える後方の位置(夜間にあつては、その船舶の第二十一条第二項に規定するげん灯のいずれをも見ることができない位置)からその船舶を追い越す船舶は、追越し船とする。
3 船舶は、自船が追越し船であるかどうかを確かめることができない場合は、追越し船であると判断しなければならない。

追い越し時の信号は?
👉 狭い水道での追い越し時は汽笛信号が必要です。(第9条4項狭い水道等おける追越し)
右側から追い越す → 長音2回+短音1回(「ーー・」)
左側から追い越す → 長音2回+短音2回(「ーー・・」)
追い越される船の同意 → 長音1回+短音1回+長音1回+短音1回(「-・-・」)
👉狭い水道以外での追越しを行う場合には追越し信号はしなくてもよい
👉ただし、予防法に基づいて針路を転じる場合は右転なら短音一回、左転なら短音二回を鳴らさなければならない。

関連法令
4 第十三条第二項又は第三項の規定による追越し船は、狭い水道等において、追い越される船舶が自船を安全に通過させるための動作をとらなければこれを追い越すことができない場合は、汽笛信号を行うことにより追越しの意図を示さなければならない。この場合において、当該追い越される船舶は、その意図に同意したときは、汽笛信号を行うことによりそれを示し、かつ、当該追越し船を安全に通過させるための動作をとらなければならない。
海上衝突予防法第9条4項
4 船舶は、互いに他の船舶の視野の内にある場合において、第九条第四項の規定による汽笛信号を行うときは、次の各号に定めるところにより、これを行わなければならない。
海上衝突予防法第34条4項
一 他の船舶の右げん側を追い越そうとする場合は、長音二回に引き続く短音一回を鳴らすこと。
二 他の船舶の左げん側を追い越そうとする場合は、長音二回に引き続く短音二回を鳴らすこと。
三 他の船舶に追い越されることに同意した場合は、順次に長音一回、短音一回、長音一回及び短音一回を鳴らすこと。
1.2 海上交通安全法(特定海域:東京湾・伊勢湾・瀬戸内海)
どんな場所で適用される?
👉 東京湾・伊勢湾・瀬戸内海など、船の交通量が非常に多い海域の適用航路を航行している追越し船に適用される。
追い越しはできる?
👉 追い越し可能な区間と禁止区間がある!
- 追い越しが許可されている区間 → 追い越しOK
- 追い越し禁止の区間 → 船舶の混雑を防ぐため、追い越し禁止
🚨 禁止区間でも、以下の場合は例外的に追い越し可能!
- 海難を避けるため
- 人命や他の船舶の救助が必要な場合
- 特定の遅い船舶(漁船など)を追い越す場合
一部の追い越し禁止の区域を除いて原則として航路内の追越しは認められている。
追い越し時の信号は?
👉 海上交通安全法6条の規定により以下のような汽笛信号を行います。
右側から追い越す → 長音1回 + 短音1回(ー・)
左側から追い越す → 長音1回 + 短音2回(ー・・)

- 海上交通安全法の追越し信号は「警告の意味合い」が強く、追越しの通知を目的とする。
- 追い越される船が積極的に協力する必要はなく、針路・速力を維持するのが原則。
- 追い越し禁止の区間では、そもそも追い越し信号を送ること自体が禁止される。
追越し船が航路を航行し追い越される船が航路外を航行している場合は?
航路において他の船舶を追い越す場合に該当するため汽笛信号を行うことにより、追越しの意図を知らせなければならない。

関連法令
第六条 追越し船(海上衝突予防法第十三条第二項又は第三項の規定による追越し船をいう。)で汽笛を備えているものは、航路において他の船舶を追い越そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。ただし、同法第九条第四項前段の規定による汽笛信号を行うときは、この限りでない。
海上交通安全法 第6条
第五条 法第六条の規定により行わなければならない信号は、船舶が他の船舶の右げん側を航行しようとするときは汽笛を用いた長音一回に引き続く短音一回とし、船舶が他の船舶の左げん側を航行しようとするときは汽笛を用いた長音一回に引き続く短音二回とする。
海上交通安全法施行規則 第5条
1.3 港則法(特定の港湾:東京港・横浜港・大阪港など)
どんな場所で適用される?
👉 特定の港湾内の航路や停泊エリア
追い越しはできる?
👉 基本的に港則法の航路内では追い越し禁止!
ただし、一部の港の航路では例外的に認められています。(京浜港・名古屋港・関門港の一部の航路)
👉 航路外で追越しを行う場合は海上衝突予防法が適用されます。
🚨 海上交通安全法と港則法の航路は異なるものなので、港則法の航路での追い越し禁止を安全法の航路と誤認しないように注意が必要です。

追い越し時の信号は?
👉 港則法では原則、航路内での追越しは認められていないため、追越し信号は規定されていません。信号よりも事前の無線連絡が重要です。
👉 追い越しが許可されている場合でも、慎重な操船が求められます。
関連法令
第十三条 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
港則法 第13条
2 船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。
3 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。
4 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。
1.4 三法の追越しについてまとめ
| 適用法 | 適用海域 | 追越しの可否 | 信号・特別なルール |
| 海上衝突予防法 | 一般海域 | 追越し可能 | 狭い水道等での追越しの場合追越し信号が必要 |
| 海上交通安全法 | 東京湾・伊勢湾・瀬戸内海 | 一部を除き可能 | 状況に応じて海上衝突予防法の信号と使い分ける必要がある |
| 港則法 | 特定港の航路 | 原則禁止 | 一部追越しが認められている |
海上交通安全法が適用される航路内での追越し信号は?
「海上交通安全法第6条(追い越し信号)」と「海上衝突予防法第9条(狭い水道での追い越し)」の関係を理解して適切に使い分けることは非常に重要です。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
海上交通安全法 第6条とは?
(追越しの場合の信号)
海上交通安全法第6条
第六条 追越し船(海上衝突予防法第十三条第二項又は第三項の規定による追越し船をいう。)で汽笛を備えているものは、航路において他の船舶を追い越そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。ただし、同法第九条第四項前段の規定による汽笛信号を行うときは、この限りでない。
✅要約すると
航路内で追い越しを行う場合は、汽笛信号を用いて追い越しの意思を伝えることが義務付けられています。
しかし、海上衝突予防法の狭い水道等における追越し信号の規定を適用することもできます。
- 海上交通安全法の信号は「警告の意味合い」が強く、追い越しの通知を目的とする。
- 海上交通安全法の追越しは追い越される船が積極的に協力する必要はなく、針路・速力を維持するのが原則。

海上衝突予防法 第9条4項は?
第十三条第二項又は第三項の規定による追越し船は、狭い水道等において、追い越される船舶が自船を安全に通過させるための動作をとらなければこれを追い越すことができない場合は、汽笛信号を行うことにより追越しの意図を示さなければならない。
海上衝突予防法 第9条4項抜粋
以上から、海上衝突予防法が適用されるの狭い水道等における追越しでは、協力動作を求める場合において汽笛信号を行う必要があります。
そのため、追い越される船は追越しに同意した場合は同意信号(-・-・)によって意図を示し、協力の動作を取らなければなりません。
場合によっては、追い越される船が追越しに同意できないときはその追越しを拒否することが可能です。

- 海上衝突予防法の信号は「追い越しの承認を求める」ものであり、追い越される船の協力を前提とする。
- 狭い水道では、追い越しが危険な場合、追い越される船は追い越しを拒否できる(その場合、追い越し船は避航する必要がある)。
- 追い越しを許可した場合、追い越される船は状況に応じて速力調整や針路変更などで協力することが求められる。
まとめ
今回は、海上三法における追越し船の航法について徹底解説しました。
操船するうえで、法令の正しい理解は非常に重要です。
誤った理解で操船してしまうと安全運航を脅かすのみならず、事故時に海難審判でも不利になってしまいます。
追越しの信号や、追越しの禁止など混同しやすいので海技士試験を受ける前に整理しましょう。
参考図書
この記事を執筆する際に以下の資料を参考にしました。細かい法令の解釈や図解も充実しているので、海技士試験の勉強でも大活躍です。海技士試験を確実に合格したいなら必読の三冊です。学生時代からお世話になっており、就職した今も見返すことがあります。
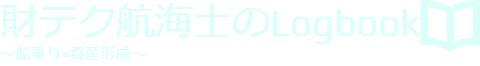



コメント